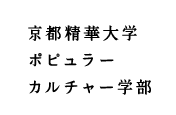2016・3・24授業紹介,読みもの
![]()
音楽家にとってのアート&サイエンス ―― 細野晴臣客員教授特別講義
2015年12月10日、ポピュラーカルチャー学部客員教授である細野晴臣さんの特別講義が開かれました。過去5回の総集編に続き、音楽コース2回生の堀江元気さんが寄稿したレポートを掲載します。
前回の講義から約1年ぶりとなる、待望の通算第6回目の特別講義が行われた。これまでの講義内容とは少し指向が異なり、物理学・自然科学の歴史や最先端のテクノロジー、果ては宇宙の原理にまで話題が及んだ。今回は、アート(=人間がつくるもの)とサイエンス(=自然がつくるもの)に対して、音楽家はどのように接続していくべきか、というテーマ設定である。
自然との調和を図る Daisy World
開講のチャイムが鳴り響くと、細野は、おもむろに自身の生家付近の略地図を描き始めた。かねてより東京の白金あたりには大きなイチョウ並木が植わっていたが、数年前、そこの一部が伐採されたことに大変なショックを受けたそうだ。また現在の自宅の駐車場にあった立派な桜の木も、邪魔だという理由で勝手に切られてしまった。交通整備などの都市開発を敢行するために、無闇に木を伐採するといった人間のエゴによって、植物や自然との共生関係が崩れていくことを、細野は非常に憂いている。
植物は、地球全体でひとつの意識を保有し、世界中の隅々まで張りめぐらされているのではないかと細野は考えている。アマゾンの原生林などで木が伐採されるたびに「全世界の木々が悲鳴をあげる」のだという。生命の起源は植物であって、人間はその遥か後に誕生したため、植物にとって人間は後輩にあたる。人々はあまりに自然界への敬意を忘れているのだ。
 植物が緑色なのは、光が葉に当たって緑の色素が反射し、それを人間の網膜が感知するためである。緑は光の成分のなかで一番エネルギーが強いが、なぜ吸収せずに反射してしまうのだろうか。光をそのまま取り入れた方が、植物にとっては有効であるはずだが、光合成によって光は酸素という別のエネルギーに変換される。つまり植物は他の生物のためにエネルギーを分け与えているのである。
植物が緑色なのは、光が葉に当たって緑の色素が反射し、それを人間の網膜が感知するためである。緑は光の成分のなかで一番エネルギーが強いが、なぜ吸収せずに反射してしまうのだろうか。光をそのまま取り入れた方が、植物にとっては有効であるはずだが、光合成によって光は酸素という別のエネルギーに変換される。つまり植物は他の生物のためにエネルギーを分け与えているのである。
環境学者のジェームズ・ラブロックは、地球が生物の相互作用により恒常的な環境をつくっているというガイア理論を唱え、雛菊の色の違いによって太陽光が与える気温の変化を調整する“デイジー(=雛菊)・ワールド”を提唱した。細野は、この考え方にいたく共感し、色の多様性が増すほど地球上のバランスは保たれるという仮想世界に魅せられた。自身の主宰するレーベル「Daisy World」はこれに由来するとのこと。
勢いづくアートの未来予想図とは
私たちは「アート」という言葉を、ただ単に「芸術」と捉えるきらいがあるが、語源を辿れば「アート」とはフランス語で「術」を意味する。つまり、芸術とはアートという言葉の狭義でしかなく、あらゆる術、すなわち人間が体得した業のひとつにすぎないという。ともすれば、一見相反する概念と思われるテクノロジー(技術)はアートに属することになる。そして現在は、このテクノロジーが幅を利かせて猛威を振るっている状況だ。
野村総合研究所が発表したニュースによると、国内610種類の職業において、それぞれ人工知能を用いた技術に取って代わられる確率を試算すると、10〜20年後に、日本の労働人口の約49%が人工知能やロボット等で代替可能になるとシミュレートされたそうだ。野村総研は、人工知能やロボットが、日本が抱える人口減少による労働力不足の問題の解決策と成りうると指摘している。こうした話題を真面目に発表する段階に差し掛かったのだと、細野は大変な関心を寄せているようだった。
近頃、人工知能に関するテーマで必ず話題に上がるのが、人工知能が人間の能力を超えてしまうような技術的特異点を指す“シンギュラリティ”である。またその転換時期が、2045年という具体的な数値が設定されているためか、技術者のコミュニティだけに留まらず、世界中で賛否両論が起こって議論が続けられている。そうした流れの中で、グローバルな大企業はこぞってイノベーション企業と手を組み、莫大な資本を投入して人工知能の研究を進める。また検索エンジン大手の会社は、世界中の膨大な情報や地球上のあらゆる地図を収集して、将来的にはそのすべてを人工知能に移植するという都市伝説さえ囁かれるのが、現代のテクノロジーの状況だという。将来的に人工知能が人間を滅亡へと追いやるのかはさておき、こうした混沌とした状況を注視する姿勢は持っておくべきであると細野は語った。
サイエンスのなかにヒントがある
 さて、そうしたアートの動きに対してサイエンスはどうか。アインシュタインの一般相対性理論の発見からちょうど100年のアニバーサリー・イヤーということも重なって、最近は物理学・自然科学に没頭しているという。細野が中学生の頃から心酔するのは、定常せずに際限なく膨張し続ける宇宙の原理である。未だに数多くの謎を秘める宇宙科学の研究分野では、刺激的な仮説も多く、なかでもとりわけ注目しているのが、“超ひも理論”だそうだ。
さて、そうしたアートの動きに対してサイエンスはどうか。アインシュタインの一般相対性理論の発見からちょうど100年のアニバーサリー・イヤーということも重なって、最近は物理学・自然科学に没頭しているという。細野が中学生の頃から心酔するのは、定常せずに際限なく膨張し続ける宇宙の原理である。未だに数多くの謎を秘める宇宙科学の研究分野では、刺激的な仮説も多く、なかでもとりわけ注目しているのが、“超ひも理論”だそうだ。
1984年、超ひも理論はマイケル・グリーンとジョン・シュワルツの二人の理論物理学者によって脚光を浴びた。大まかに定義すると、超ひも理論とは、これまで主流派だった「物質の最小単位は素粒子である」という考えではなく、「最小単位は“ひも”である」という画期的な発想である。“ひも”を究極の最小単位と捉え、長さ10のマイナス35乗メートル、運動する時空は10次元とした。当時は批判の声も少なくなかったが、超ひも理論は宇宙のすべての力学を数学的に構築しようと試みる意欲的ものだった。
一般相対性理論を駆使したブラックホールの解析では、発生源が面積はゼロ、重力も無限となり、数学的矛盾が生じて理論は破綻してしまう。しかし、超ひも理論を用いれば、数式に整合性が生まれて矛盾は解消するらしい。一般相対性理論と量子力学を等式で結べるこの理論は、徐々に研究者の間で支持の声が集まり、有効な理論だという認識が広まっている。
現在では、メンブレン(=膜)を単位とするより発展的な“M理論”との相互作用の効能について研究がなされているそうだ。ひもにせよ、膜にせよ、振動によって粒子が形成されるとするならば、振動によって生じる周波数、つまり音が万物の源であるという解釈ができるのかもしれない。「要するに、この世は音でできている」のだと細野は述べた。
音楽家にとって、テクノロジーやテクニックは直接的な問題であるが、サイエンスをクリエイティブに利用する者は意外と少ないと細野は指摘する。細野曰く「サイエンスのなかにヒントがある」という。本講義では、サイエンスの重要性をたびたび強調していた。
感覚をちょっとだけ拡げてみる
超ひも理論を発見する以前、グリーンとシュワルツは、数式の試行錯誤の段階で完全数の“496”という数字が頻出することに気づいた。彼らはこれを「神が創造した数字(ネイチャー)である」と熱狂し崇めたそうだ。細野はこの興奮こそ、芸術の本質だと指摘する。サイエンスにも芸術的瞬間は訪れるのだ。芸術とは、閃くことの喜び、またはそれに伴う得も言われぬ興奮のことを指す。あるいは、普段使っている脳細胞の少し外側にある未知の領域を刺激する行為、つまり「感覚をちょっとだけ拡げてみる」ことであると細野は表現した。
我々の脳の実際は、様々な外的な刺激を取捨選択し、慣れ親しんだ情報を好んでインプットする性質が支配的だ。音楽の場合、理解不能な曲よりも、それまでの音楽体験に則した曲を聴きたくなる。ところが、細野はそうした既存の感覚領域から少し外れた音楽を人一倍求めており、50〜60年代のヒット曲は、その欲求に応える「似ているけど何か違う/新しい」音楽であったという。しかし、現在は感覚の領域内で全て済ましている時代で、ワクワクすることはめっきり減ってしまったらしく、自身は「今の時代は好きでもないし、売れたくもない」と語気を強めた。
人間の伝統文化とは、過去の人が拡げた感覚を自らの遺伝子に組み込み、時には再検証する過程を経て、新しい感覚を加えては次世代へと繋げていくものである。したがって、未知の領域へと感覚を拡げていこうとする意気込みがないと面白くない。そう細野は言う。全くの繰り返しではなく、あるパターンのなかで自分の解釈や発見を具現化して、音楽の伝統にほんの少しのオリジナルな要素を付け足していくのが、音楽家の在るべき姿だと語った。
最後に、聴講に訪れたミュージシャン・作曲家志望の学生に対して細野は、「将来どんな音楽をつくるのか楽しみにしているので、また聞かせてくださいね」とエール送って、後進への期待と飽くなき好奇心を覗かせていた。
イラスト: 寺岡奈津美
→ 細野晴臣客員教授特別講義レポート「戦後日本とアメリカのポピュラー音楽の伝承」