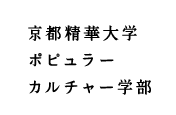2016・5・13授業紹介,読みもの
![]()
音楽の背景、背景の音楽 ―― 岸田繁客員教員特別講義
2016年度より、ロックバンドくるりの岸田繁さんがポピュラーカルチャー学部の客員教員に就任しました。前期授業期間が始まって間もない4月18日、さっそく第1回の特別講義が実施されました。同じく客員教員を務める細野晴臣さんの講義レポートを手掛けてきた音楽コース3回生の堀江元気さんが、今回もレポートを寄稿してくれました。
2016年4月1日をもってポピュラーカルチャー学部の客員教員となった岸田繁が、就任後間もない4月18日に初回講義を行った。岸田は、やや緊張した様子を覗かせながらも、持ち前のユーモラスな語り口でフロアの学生と積極的にコミュニケーションを取った。両者は、意識を共有させながら演習型の講義を進めていった。様々な場所やシチュエーションで流れる音楽を想像し、その選曲にはどのような意図や目的があるのかを推察するという内容である。

音楽が流れている空間を想像しよう
本講義に先立って公開されたインタビューにおいて、岸田は、具体的な場所やシチュエーションで、どういうふうに音楽が聴かれるべきなのかを掘り下げたいと述べていた。それを踏まえて、今回は、以下のような設定で任意の音楽が流れている空間を想像し、実際に自分がそこの当事者ならばBGM(バック・グラウンド・ミュージック)としてその音楽はどういう聴こえ方をするのか、という実験的な比較検証が行われた。
【ケース1】 歯の治療のために歯科医院に訪れ、遠くで患者が歯を削られている音を耳にしながら、待合室でオレンジページなどを読んでいるとしたら
岸田は、まずビートルズの「イエスタデイ」の原曲とオルゴールアレンジ・ヴァージョンを流した。どちらがBGMとして良かったかという質問に対して、原曲派の学生は「歯を削られている音をかき消してくれそう」だと言い、オルゴール・アレンジ派の学生は「お医者さんが優しそうだから」と答えた。岸田は笑みを浮かべ、次に両極端な2曲を提示した。
パンテラ「ビカミング」のヘビーメタル・サウンドが流れた瞬間、会場では大きな笑い声が起こった。金属的な響きをもった爆音ギターと過激なデスボイスが、想像上の歯医者を、巨大なドリルをもった悪魔に変貌させてしまったのかもしれない。筆者は虫歯は無いが、急に奥歯が痛んだ気さえした。その後に流れたのは、エリック・サティの「ジムノペディ第1番」というクラシックの定番曲。これには全員しっくりきたようで深く頷いた。

【ケース2】 恋人、または憧れの人との性的な行為(内容に関しては個人に委ねる)に夢中になっているとしたら
こういったシチュエーションの場合、そもそも音楽が必要なのかという問題がある。事実、不必要だと考える学生が大多数だった。仮に音楽を流すとするならば、どの曲が雰囲気を壊さずに、エロティックなムードをより一層引き立てられるのだろうか。そういう意味では、カーペンターズの「イエスタデイ・ワンス・モア」のように、サビで急に盛り上がるなどの楽曲の構成がはっきりしている音楽は、行為の妨げになる可能性があると岸田は指摘する。楽曲自体に愛着があったとしても、BGMとして効果的に機能するとは限らないのだ。その点ジョス・ストーンの「フェル・イン・ラブ・ウィズ・ア・ボーイ」は、腰に訴えかけるベースと喘ぎ声のような女性ボーカルが印象的なファンク調の曲で、ここでの親和性は高いように感じた。
【ケース3】 引き戸の入り口から暖簾をくぐって、格式高い石畳や粋な梁を眺めながら奥の席に座り、職人手打ちの天ぷらそばを堪能しているとしたら
岸田は、ジョン・コルトレーン&デューク・エリントンの「イン・ア・センチメンタル・ムード」と宮城道雄の「春の海」を並べ、どちらの天ぷらそばが美味しかったかと感想をフロアに求めた。すると圧倒的に後者の方が美味しかったという人が多く、「日本らしい音楽が合う」「ジャズでは箸が止まる」といった意見が聞かれた。岸田は「(ジャズだと)そばではない味がした」との返答をとくに面白がった。
細野晴臣の「泰安洋行」を流すと、再び教室が笑いに包まれた。岸田は、この曲を聴くと「天ぷらそばより、パクチーが入ったフォーを食べたくなる」のだと述べた。BGMの曲調や使用楽器によって――想像上ではあるが――味覚に変化が生まれるという指摘は示唆に富んでいる。

その空間におけるBGMの意味
我々が営む現代の生活環境は音楽に溢れている。上記の例は、その中に存在するほんのごく一部に過ぎない。スーパーマーケット、ショッピングモール、コインランドリー、ゲームセンター、レストラン、ホテル、ショールーム、空港、駅、喫茶店、大型書店、高層ビル、遊園地……。これらの空間には必ずというほど何らかのBGMが流れている。都市空間のなかで暮らす人間にとってBGMは、環境音として、もはや社会構造を組織する細胞と化しているのだ。
かつての価値基準では、毒にも薬にもならないものだと省みられることが少なく、大衆から無視され続けてきた歴史があった。しかし、ある場所やシチュエーションにおける音楽の影響力が、どれほど絶大であるかは容易に想像がつくはずだ。アメリカでは、BGM供給会社の代名詞とされるミューザック社が、20世紀前半から現在までこの分野において先進的なポジションに君臨している。日本でも、1961年に創業した大阪有線放送社(現USEN)が事業を拡大し、有線ラジオ放送の最大手企業となった。両社は「清潔感のあるクリニック向け」「家庭用美食空間ジャズ」など生活習慣に馴染むプレイリストを作成し、小売店や施設などに配信するビジネス・モデルを確立させた。
例えばケース1で見てきたように、歯科医院をはじめ多くの病院では、既成の曲をオルゴール・アレンジした曲や、ゆったりとしたテンポのクラシック音楽が収録された有線放送チャンネルを使用している。だが、なぜパンテラではなくエリック・サティが望まれ、なぜビートルズの原曲ではなく陳腐なオルゴールの調べが採用されるのだろうか。岸田は、その場所で求められる音楽をめぐる取捨選択の理由を考察する必要があるのだという。
 一般的に、受診に訪れる患者は、大抵は恐怖や痛みあるいは悩みを抱えている。つまりこの状況下では、不安や緊張を和らげる役割を担うBGMを流すのがベストだと考えられる。とするならば、刺激が少なく控えめな音で、かつリラクゼーション効果が期待できる音楽に限定されていく。そういった点でメタルではなくクラシックが選ばれ、「イエスタデイ」はオルゴール化されるのだ。ただ単に、往年の名曲が質の悪い編曲者によって劣化したわけではない。曲の善し悪しではなく、その空間のニーズに合った音楽こそが、適切なBGMと呼べるのだろう。
一般的に、受診に訪れる患者は、大抵は恐怖や痛みあるいは悩みを抱えている。つまりこの状況下では、不安や緊張を和らげる役割を担うBGMを流すのがベストだと考えられる。とするならば、刺激が少なく控えめな音で、かつリラクゼーション効果が期待できる音楽に限定されていく。そういった点でメタルではなくクラシックが選ばれ、「イエスタデイ」はオルゴール化されるのだ。ただ単に、往年の名曲が質の悪い編曲者によって劣化したわけではない。曲の善し悪しではなく、その空間のニーズに合った音楽こそが、適切なBGMと呼べるのだろう。
このように、音楽がその場所あるいは人間にもたらす作用・効能を検証し、より優れた空間デザインを提案していくことができれば、新しい音楽の可能性が見出せるはずだと岸田は語っている。また、今後はBGMにまつわる音のノウハウを深化させ、学生と共に店舗のBGMを考えたいという構想を明かした。
音楽を聴くことから始まる
野村克也(プロ野球)の「結果は重要だが、プロセスを大事にしろ」という言葉を、岸田は常々考えているそうだ。一般に普及している仕組み(=結果)には、必ずそこに至るまでの過程(=プロセス)を経ている。今回取り上げられたBGMに関しても、元からそこで鳴っていたのではなく、空間に適した音楽について考え抜いた人々によって生み出された産物である。さらに、ある曲が作られて、聴衆がその音楽を受容するまでプロセスには、多種多様な職種の人間が関わっていることを意識し、それぞれの構成要素があってこそ成立している事実を改めて見直さなければならない。
岸田は、開講前に実施された学生向けの希望進路に関するアンケートに目を通しながら、現在の音楽業界は人材不足であると説明してした。音楽関係の仕事をするには、その道のプロフェッショナルであることが求められる。自身もプロのミュージシャン/作曲家としてキャリアを積んできたが、音楽を作って伝えるための必要な知識や技術を得るためには、今なお継続的な学習が必要不可欠だと感じているという。

しかし、岸田は、音楽に関わる仕事を志望する人間であれば、そうした個々の専門的な能力を養う以前に絶対に真剣に取り組むべきは、「音楽を聴く」ことだと力説する。要するに音楽を聴いて感動する体験が大切なのだ。その音楽のどこが良いのか、なぜ良いと思ったのかを思案し、作り手の意図・目的を分析するなど客観的な視点を持つこともまた必須である。名の通ったミュージシャンの傑作でも、無名のバンドマンのライブ演奏でも良い。あるいはBGMのような生活空間のなかに潜む様々な音に耳を傾けてみるのも良いだろう。その音楽の良さを一つでも多く発見できれば、間違いなく自分の肥やしになるという。
ギターの早弾きができたり、和声の理論をマスターしていたりするのも、もちろん有意義である。しかし、音楽を聴いて、音楽から受けた感動を体験として知っていること、その音楽がかっこよく聞こえたという経験を持っている方が、より大事になってくる。岸田は重ねてそう強調していた。
→ くるりに学ぶ、プロのスタジオワーク ―― 岸田繁客員教員特別講義
→ 哀愁のマイナーセブンフラットファイブ ―― 岸田繁客員教員特別講義