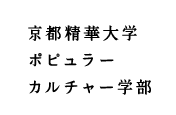2016・12・1授業紹介,読みもの
![]()
哀愁のマイナーセブンフラットファイブ ―― 岸田繁客員教員特別講義
2016年6月15日、岸田繁客員教員の第3回特別講義が実施されました。4月の第1回、5月の第2回に続き、恒例となった受講生によるレポートを掲載します。
今回の講義では、自分が表現したい感情や風景と作曲技術を結びつけて音楽に昇華させるため、コード理論の領域にまで及んだ。ここでの岸田は、バンドマンというよりも、作曲家/コンポーザーとしての側面が顔を覗かせていた。音楽はもちろん、とりわけソングライティングに関心のある学生には、実りの多い講義になったのではないだろうか。
「聞く」と「聴く」の違い
「(耳を使って)きく」という言葉には二通りの表し方がある。「聞く」と「聴く」。両者の意味の違いを調べるために辞書を引くと、前者は「音や声を感じとる。また、その内容を知る」、後者は「注意して耳に入れる。傾聴する」との記述がある。すなわち、知覚する側の意識の違いによって使い分けられている。差し当たって英語の「hear」と「listen」の違いと言えば理解しやすいかもしれない。
 今回は、初回講義のBGMにまつわる話題を引き継ぎ、意識的に音を「聴く」とはどういうことか、また、音楽から受け取るイメージはリスナーの経験則によって変化するのか等、具体例を示しながらレクチャーすることが授業の主軸に据えられた。
今回は、初回講義のBGMにまつわる話題を引き継ぎ、意識的に音を「聴く」とはどういうことか、また、音楽から受け取るイメージはリスナーの経験則によって変化するのか等、具体例を示しながらレクチャーすることが授業の主軸に据えられた。
まず、曲に抑揚がなく「聞き流せる」というのが、BGMの性質を特徴づける上でひとつポイントになってくるのだと岸田は指摘する。例えば、斉藤和義「歩いて帰ろう」の原曲とクレモンティーヌのボサノバ・カバーを比較してみると、クレモンティーヌの方がテンポ、曲調、音色など「聞き流せる」要素は多く含まれている。一番の要因は、ポルトガル語のため歌詞が耳に入りづらいこと。意識的に聴取する対象としない(=注意深く聴かない)ことが、BGMとして有効であるのは、前々回の講義で確認した通りだ。
一方、音を「聴く」という概念をどう捉えるか。この事象を解き明かす最良のテキストとして岸田が引用したのが、松尾芭蕉の「古池や 蛙跳びこむ 水の音」である。ここで詠まれている客体は、池に跳びこんでいる蛙ではなく、水の音のような微細な音すら聞こえる静寂な空間。そうした場所に身を置いて、水の音に限らず、自然のなかにある多彩な環境音を聴いて趣を感じ取っているのだ。そのため、この俳句は「聴く」という行為に対する優れた批評である、と岸田は評している。
ただ単に音を漠然と「聞く」のではなく、注意深く「聴く」ことで、その対象について分析的に考察できたり、あるいは作り手としての表現の可能性が拡げられたりするのだ。すべては音を「聴く」ことから始まる。これこそ岸田の各授業に通底するメインテーマであり、繰り返し強調したいメッセージである。
人生経験によって音楽の聴こえ方は変化する
ベートーヴェンが書き上げた交響曲第6番の第一楽章には、自身によって『田園』という標題が付けられている。この『田園』が題材となって、異なる二枚の写真をスクリーンに映し出しながら音を聴き、リスナーが想起するイメージの相違を検証した。

まず、田んぼに囲まれた線路を走る電車(キハ52系)の写真が表示され、次に、岸田がウィーン滞在時に撮影したブドウ畑の写真へと画面が切り替わる。同じ田園風景でありながら、そこから受け取る音の印象は劇的に変化することがわかるだろう。日本人が想起する田園(=田んぼ)と、作曲者のベートーヴェンが想定していた田園(=ブドウ畑)との間には、著しい想像力の乖離が横たわっている。音楽というのは、潜在的にそうしたミスリーディング作用を常に内包しており、作り手の意図に関係なく、受け手のイメージや知識いかんで簡単に変化するもの。つまり、音楽の享受の仕方は、受け手の人生経験によって多様化していくのである。
これに関して、岸田は、スコットランドの北部エジンバラ出身のトラヴィスを挙げ、このロックバンドの曲を現地で聴いた時と日本で聴いた時では、音の響き方が全く違って聴こえた体験を紹介した。それまで特別トラヴィスを評価していたわけではなかったが、現地の空気で呼吸しながら聴いたその音楽は格別に素晴らしいものだったという。生活を営む人々の集合的な経験が文化を形成し、その土地固有の音楽性が醸成されていく。岸田はこの現体験を通して、ある音楽に対する価値観は、絶対的に固定化されているのではなく、環境や経験則に応じて流動的に変容していくのだと痛感したそうだ。
岸田は、野村克也の「野球人たる前にいち社会人たれ」という名言を引用し、「音楽家たる前にいち社会人たれ」という標語を掲げる。岸田自身は、この「社会人たれ」を、社会の規律を守って実直に生きろという意味ではなく、世の中の多くの人々が人生で経験する喜怒哀楽を知っておくことで、作り手は受け手の心を打つ表現ができるようになるという意味で捉えている。ラブソングを書く場合でも、ただ単に「好きだ」と連呼する曲よりも、フラれる気持ちや痛みを知って「好きだ」と歌う曲の方が、深みや芳醇さも増してくる。表現者としての幅を拡げるためにも、あるいは作品が与える感度を上げるためにも、いろんな人生経験を積んでほしいと述べている。
表現したい気持ちを和音に置き換える
音楽をより良く楽しむためのアティチュードに重きが置かれていた講義の前半部に対して、後半では、自分が表現したい感情や風景を実際的な作曲技法を用いて、具現化するための音楽理論に焦点が当てられていく。
音楽を生業として日々の生活を送っている岸田にとって、音楽を聴くことは何よりの幸せであるが、それと同時に、曲から与えられる感動は一体どこから生まれてくるのかを常に追求しているそうだ。くるりのファーストアルバム『さよならストレンジャー』の制作中に、当時自分が好きだったテイストの音楽を分析的に聴き続けた結果、それらの曲に共通する、あるコードに気づいたという。
その要素を含んだ音楽の例として挙がったのが、アストリッド「アンタイトルド2」、カルリーニョス・ブラウン「ソウル・バイ・ソウル」、ジェリーフィッシュ「ジョイニング・ア・ファンクラブ」、藤田陽子「スフィア」。これらの共通するコードとは、Ⅳ♯m7♭5(音階の第4音の半音上を根音としたマイナーセブンフラットファイブ)である。

岸田は、この和音が持つコード感を感覚的に理解するため、まずは、基本のコード進行を打ち込んだ音源を鳴らしながら、それに合わせて聴講生全員でメロディを歌唱する方式を採った。最初のコード進行は、キーをCに設定した場合の、C(トニック)→Am(トニック)→F(サブドミナント)→G(ドミナント)→C(トニック)という基礎的なケーデンス。このコード進行上では、Cメジャースケール(Aマイナースケール)の音で構成されるメロディが乗りやすく、形式的に無理のないオーソドックスな響きが得られる。しかし基本形であるがゆえに、何の意外性もない予定調和な進行になってしまう傾向がある。そこで岸田は、F(サブドミナント)の代理として、F♯m7♭5を使用する。それによって単純だったコード進行に哀愁感が加わり、メロディもまろやかに響くように感じられた。
 次に、くるりの「春風」の2番のコーラス(「遠く汽車の窓辺からは」「ここで涙が出ないのも」の部分)を同様の方法で検討する(※原曲のキーはEだが、便宜上Cに移調する)。この楽曲はメロディから作ったそうで、最初につけたコードはC→G→C→Fという至ってシンプルなものだった。ところが、岸田曰くこのコード進行では「春風が見えなかった」という。自身の思い描いた感情や風景をなるべく忠実に表現したいと考えた時、自分の引き出しの中で最もそのシーンに適したコードが、件のマイナーセブンフラットファイブだった。岸田にとってこの和音は「心の浮遊感の演出」だと説明する。Fの代わりに、F♯m7♭5を使用。心の動きを表すような分数コードも巧みに導入し、最終的にはC→G/F→C/E→F♯m7♭5という進行となった。メジャースケールの構成音には無いF♯の音が、調性感を揺らがせ、曖昧な響きを演出しているように感じられた。この和音は、我々の考える“くるりっぽさ”のひとつの要素であると言えるかもしれない。
次に、くるりの「春風」の2番のコーラス(「遠く汽車の窓辺からは」「ここで涙が出ないのも」の部分)を同様の方法で検討する(※原曲のキーはEだが、便宜上Cに移調する)。この楽曲はメロディから作ったそうで、最初につけたコードはC→G→C→Fという至ってシンプルなものだった。ところが、岸田曰くこのコード進行では「春風が見えなかった」という。自身の思い描いた感情や風景をなるべく忠実に表現したいと考えた時、自分の引き出しの中で最もそのシーンに適したコードが、件のマイナーセブンフラットファイブだった。岸田にとってこの和音は「心の浮遊感の演出」だと説明する。Fの代わりに、F♯m7♭5を使用。心の動きを表すような分数コードも巧みに導入し、最終的にはC→G/F→C/E→F♯m7♭5という進行となった。メジャースケールの構成音には無いF♯の音が、調性感を揺らがせ、曖昧な響きを演出しているように感じられた。この和音は、我々の考える“くるりっぽさ”のひとつの要素であると言えるかもしれない。
この音楽の“ココが好き”を突き詰めていく
近頃、岸田が惹かれているのは、バルトークの「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」第2楽章の和声だという。従来のクラシック理論に収まらない前衛的な手法を取り入れている楽曲であるがゆえ、まだ自身では詳細に分析できないが、将来的に皆んなに説明できればと話していた。キャリア20周年を迎え、12月の初演で披露されるクラシック交響曲『交響曲第一番』を書き上げた現在も、古今東西の音楽にアンテナを張り巡らせて、自分が気になったものを掘り下げて勉強していく岸田のスタイルは、相変わらず健在のようだ。
今回の講義では、音楽の作り手を念頭に置き、コード進行の話題が取り上げられた。しかしあくまで重要なのは、コード進行に限らず、音楽を注意深く聴いて、自分が好きだと感じるポイントをとことん追求することである。メロディ、アレンジ、リズム、音色、歌詞など、関心を寄せる部分は人それぞれ。自分ならではの着眼点を携えつつ、様々な人生経験を通して感性を養っていくこと。そして学び続けること。それが何よりも大切であると岸田は説いていた。

→ 音楽の背景、背景の音楽 ―― 岸田繁客員教員特別講義
→ くるりに学ぶ、プロのスタジオワーク ―― 岸田繁客員教員特別講義