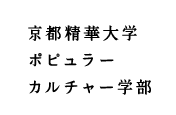2015・12・7授業紹介,読みもの
![]()
細野晴臣客員教授特別講義レポート「戦後日本とアメリカのポピュラー音楽の伝承」前編
来たる12月10日、細野晴臣ポピュラーカルチャー学部客員教授による特別講義が開かれます。2013年の学部開設以来、細野さんは、自身の音楽体験と、そこに大きな影響を及ぼしてきたアメリカ文化という一貫したテーマのもと、さまざまな観点から講義を展開されてきました(第5回のレポートはこちら)。約1年ぶりとなる講義を控えて、これまでの全5回の講義内容をおさらいすべく、音楽コース2回生の堀江元気さんに講義レポートを寄稿していただきました。前後編に分けて掲載します。
京都精華大学ポピュラーカルチャー学部の客員教授を務める細野晴臣が5回にわたり行ってきた特別講義。多岐にわたる話題の中でも全講義に通底しているテーマは“アメリカのポピュラー音楽の伝承”である。
現代における日本の音楽シーンの基盤となり、その後あらゆる音楽の誕生や発展において重大な役割を担ったアメリカのポピュラー音楽群。しかし細野曰く、現在は情報が溢れている割にそれを知る術がなく、自身も体験してきた音楽の歴史を伝えたいという気持ちがあるのだという。「20世紀は音楽の鉱脈。石炭や石油と同じように音楽が埋もれているわけで、そこには未知のエネルギーや新しい発見がある。僕の話の中に出てくるいろんな音楽や人物をきっかけにして掘り下げて欲しい」とのこと。
そこで今回は、アメリカのポピュラー音楽受容のキーファクターである“戦後日本”を基軸に据えて、各講義の内容を取り上げていきたい。
第1回 音楽のルーツは占領期(2013年6月13日)
記念すべき第1回目の講義は、我々日本人のルーツとは何であるのかという問いを立て、聞き手に想像を促すことから始まった。ミュージシャンたちは昔の音楽をカバーしたり英語の曲を歌ったりしてきたが、なぜ日本の音楽ではなかったのだろうか。それを考える上で、第二次世界大戦の影響は外せない。
細野は終戦2年後の1947年、東京都港区生まれ。GHQのマッカーサー主導による占領政策のもとで日本の戦後復興が行われると同時に、アメリカ文化が堰を切ったように流入してきた時代の中で幼少期を過ごす。家には無数のSP盤があった。軍歌は勿論、ベニー・グッドマンやグレン・ミラーなどの戦前のアメリカ音楽を聴いており、その中にあったブギウギを特に面白がって飛び跳ねていたそうだ。自身にとって何にも代え難い大事な経験だったとのこと。
当時の日比谷の風景も記憶に残っているそうで、戦後に解禁されたハリウッド映画を観に行く母親に抱かれた細野少年は、自動小銃をさげた米兵や軍用車両ジープが右往左往する様子を目にしていた。まさに戦後日本の歩みと共に育った世代である。小学校に入学してもアメリカの影響は色濃かった。教育にも米軍が関与し、音楽の授業では民謡などの邦楽をほとんど習わなかったらしく、自国の音楽を知らずに育ったそうだが、けして悲観しているわけではないと笑っていた。
終戦から1952年のサンフランシスコ講和条約施行までの占領期には、日本各地で土地や施設などが進駐軍に接収され、米軍基地が建設された。また、一般の日本人の立ち入りが禁じられた「オフリミット空間」が現れ、その中の進駐軍の娯楽施設であるクラブは、元軍楽隊の日本人などが雇われてジャズやカントリーを毎晩のように演奏するという音楽的洗練の場でもあった。
日本各地に現れた米軍基地に勤める兵士を慰安するために、アメリカ音楽の需要が一挙に増加する。そのニーズに応えるように、日本人のミュージシャンはキャンプ廻りをして、ジャズやカントリーを演奏することになった。彼らは、米兵の趣味に合わせるために、ラジオやレコードでアメリカの流行曲を聴いて必死にレパートリーを増やしながら学んでいったようだ。
また、進駐軍クラブで鍛えられたバンドマンの中には、渡辺晋や堀威夫など商才に長けた人々がいた。彼らがプロダクションを立ち上げて人材派遣を始め、それぞれナベプロ、ホリプロを組織して、後の芸能界の土台を築き上げることになった。占領期から米軍の大半が撤退するまでの数年間は、バンドマンによる演奏のみならず、クラブと出演者の間に入りマネージメント業務を行った仲介業者たちも含めて、戦後日本の文化的発展に寄与してきた。サウンドと興行の両面で今日のポピュラー音楽、ひいてはエンターテイメント業界の礎となったのだ。
第2回 ミュージシャンである前にリスナーだった(2013年9月21日)
前回に引き続き、我々日本人がいかにしてアメリカのポピュラー音楽を受容してきたのかというテーマだった。
前述したように、進駐軍クラブでの音楽実践には、アメリカのポピュラー音楽の受容という重要な文化的意義があった。しかし、そこはあくまで一般の日本人の立ち入りが禁じられたオフリミット空間であり、ミュージシャンや仲介業者などの一部の人々しか体験できなかった。そこで、より大衆が享受可能なメディアとして存在したのが、進駐軍専用のラジオ放送局FEN(Far East Network、極東放送網)である。
1945年9月末に前身のWVTRが開局し、その後FENと呼ばれるようになる。米兵やその家族を対象にした専用放送であったが、実際には米軍基地がある都市では一般家庭でも電波を受信できたようだ。
十代の細野は、このFENの全米のヒットチャート番組を中心に、アメリカのポップスやロックを聴くのが音楽体験のすべてだったそうで、もし仮にFENを聴いてこなければ、今頃どうなっていたか分からないという。育った環境が人を成長させ人を変えていくのだと、言葉にも力が漲っていた。
同時代には、各地にやはり同様の音楽体験をする若者たちがいた。三沢基地の電波で聴いていた大滝詠一、久留米基地の電波を聴いていた鮎川誠らも、ラジオに齧りついていた。少し下の世代の山下達郎なども含められそうだ。後にミュージシャンなど音楽に携わる仕事をする人々が総じて「FENを聴いていた」と口を揃えるほど、強力な影響力を持っていたわけだ。ラジオを通して日本人の耳を育てたと言っても過言ではないだろう。
この音楽を聴くという行為に関して細野は、当時と現在ではアプローチの手順が正反対だったことを指摘し、何よりもまずリスナーであることの重要性を説く。楽器を演奏したり曲を作ったりする以前に、とにかく聴くことが大切だという。自身もまた、ミュージシャンであることよりも、いちリスナーでいることを常に意識し、「リスナーが高じるとこうなるっていう典型」だと自己分析する。
もちろん、ラジオという極めて受動的なメディアが主流の時代と、ユーザーが能動的にアクセスするいまのネット時代とでは単純に比較はできないが、「音楽を聴いて、聴いて、聴きまくる」というプロセスは今も欠かせないだろう。並々ならぬ好奇心をもって、意識的に音楽と接することを、学生たちに要求した。