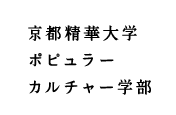2015・12・9授業紹介,読みもの
![]()
細野晴臣客員教授特別講義レポート「戦後日本とアメリカのポピュラー音楽の伝承」後編
来たる12月10日、細野晴臣ポピュラーカルチャー学部客員教授による特別講義が開かれます。2013年の学部開設以来、細野さんは、自身の音楽体験と、そこに大きな影響を及ぼしてきたアメリカ文化という一貫したテーマのもと、さまざまな観点から講義を展開されてきました(第5回のレポートはこちら)。約1年ぶりとなる講義を控えて、これまでの全5回の講義内容をおさらいすべく、音楽コース2回生の堀江元気さんに講義レポートを寄稿していただきました。前編に続き、第3回から第5回までの後編を掲載します。
第3回 ティン・パン・アレーからティン・パン・アレーへ(2014年1月31日)
この回は、はっぴいえんどのメンバーであり盟友である大滝詠一が急逝した約1ヶ月後に行われた。まだ整理がつかない現在の心境を述べて、昔を回想しながら大滝との思い出を懐かしむように語り始める。――細野晴臣と大滝詠一。同志であり常に互いの存在を意識し合う関係だった。
細野にとって大滝は「物知りすぎて怖い」「頭の中がどうなってるか気になる」存在で、彼の博識ぶりには舌をまくばかり。初めて出会った時、細野宅のオーディオセットに置かれたヤングブラッツ「ゲット・トゥギャザー」を、挨拶もなく開口一番に指摘されたときは、こいつはイケる、すごいヤツが来たなと思ったという。
70年代初頭に松本隆と鈴木茂を加えた4人で結成したはっぴいえんどが、母体となるバンドのモデルに選んだのは、アメリカ西海岸のロックバンド、バッファロー・スプリングフィールドだった。ロサンジェルスでレコーディングした3枚目のアルバムをリリースする前に解散を発表し、バンドは幕を下ろした。しかし、その際にプロデューサーを務めたヴァン・ダイク・パークスとの邂逅を機に、今まで点在しているように思われた音楽が期せずして繋がり、ひとつの大きなアメリカンポップスの流れが浮かび上がってきた。
その文脈の原点に位置したのが、良質なアメリカンポップスの生産工場「ブリル・ビルディング」である。ニューヨークのブロードウェイに拠点を置いた建物の名称で、広義的にはその周辺で作られたサウンドを指す。雑居ビルの中にアルドン・ミュージックという音楽出版社があり、キャロル・キング/ジェリー・ゴフィン、バリー・マン/シンシア・ワイル、ニール・セダカ/ハワード・グリンフィールドなどの作詞家・作曲家コンビがヒット曲を量産していく。「オールディーズ・イズ・グッディーズ」と呼ばれる、アメリカの音楽史には欠かせない黄金時代。その担い手である彼らへの敬意は忘れてはいけないという。
そして、この出版街一帯を指す名称を冠したセッション・グループ、ティン・パン・アレーは、70年代半ば、荒井由美をはじめとする気鋭のシンガーソングライターたちをバックアップした。彼らは脈々と受け継がれるアメリカンポップスの流れを汲み、「ニューミュージック」と呼ばれることになる、日本における新たなポップスの潮流を生み出すことになった。後年、戦後歌謡界を代表する職業作曲家の筒美京平は「仕事がなくなった遠因は、はっぴいえんどにある」と語ったそうだが、まさに70年代という大きな転換期を最も明解に示したエピソードとして捉えられよう。
第4回 音に空間性を取り戻す(2014年4月22日)
講義の直前に、本学に新設された友愛館の地下にあるレコーディングスタジオ「Magi Sound Studio」を見学した流れで、この回はレコーディング/音響技術についての講義となった。
第二次世界大戦の勝利による未曾有の好景気に湧いていた50年代初頭のアメリカは、顕在化していく東西陣営の対立の影響もあり、技術開発が歯止めなく行われる状況下にあった。テクノロジーの発達と戦争は不可分の関係にあり、軍需産業はしばしば音楽業界に恩恵を与えてきたことは案外知られていない。例えば今日の音楽制作には欠かせないイコライザーやコンプレッサーなどの装置は、潜水艦探知機ソナーで運用された軍事技術からの転用である。
このあたりの時期には、忠実性の高い音を志向する「ハイ・フィデリティ」の概念が一般リスナーの聴取レベルまで浸透しつつあった。録音の現場では、立体的で臨場感溢れる音像を希求し、ステレオ技術を用いた試行錯誤が行われていた。細野はこの戦後間もない頃のサウンドがとりわけ好みらしいのだが、ハイファイの旗印のもと、音の分離をよくするために各楽器の相互干渉を排除する方向へと邁進していく歴史の歩みには、強い違和感を抱いていた。
はっぴいえんどの活動期間はレコーディング技術の急速な発展と並行しており、マルチトラックレコーディングが隆盛を極める時世であった。1枚目のアルバム『はっぴいえんど(通称ゆでめん)』は4トラックだったものの、2枚目『風街ろまん』は8トラック、3枚目『HAPPY END』は16トラックと、数年間のうちにチャンネル数が倍増していく過程を、細野は間近で経験してきた。そうしたなかで、あるいはキャピトル・レコードのエコーチェンバーを使ってリミックスしたYMOのアルバムを通して細野は、ハイファイ志向の行く末が、レコーディングにおいて最も大切な要素の一つである「スタジオ内の空間性」の消滅に帰結するのだと悟ったそうだ。
90年代以降のDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)ありきの音楽制作に没頭した時期を経て、細野は近年になって再び、生演奏を基本にしたバンド編成に惹かれているという。細野晴臣名義で発表するレコーディング・セッションの場合は、コンデンサマイクに代えてリボンマイクを多用し、楽器間の音のかぶりを許容するようなセッティングで一発録りをする方法に変化したとのこと。それはある意味で原点回帰といえるだろうが、録音のスタイルは古くともけして懐古的ではなく、むしろ貪欲に、失われた「スタジオ内の空間性」の回復に努めつつ、それをブラッシュアップしようとする姿勢の現れだと、筆者は感じ取っている。
レコーディングと音響技術に関する話題の締めくくりに、洋楽をほとんど聴かないレコーディング・エンジニアが昨今増加し、ことさら低音域の処理能力が相対的に乏しくなっていると細野は指摘。音楽的な鎖国をせず、積極的に海外に出てミックスの極意で学んでいってほしいとフロアの学生たちに期待した。
第5回 音楽史の特異点(2015年1月20日)
この日の講義には、今や細野バンドのギタリストとして不可欠な存在であり、翌日に予定されているスライドギターのワークショップの講師として招かれた高田漣がゲスト参加するかたちで行われた。
キーワードとして挙げられたのは、歴史の中に埋もれた「特異点」。音楽史の流れの中でも特殊かつ希有な存在、あるいは本質的な意味で天才と称されるべき人々=特異点。このように定義した場合、とりわけ戦後日本のテレビ業界黎明期において異彩を放ったディレクター、井原高忠がその一人として挙げられるという。
井原は、50年代アメリカで人気を誇った音楽バラエティ番組『ペリー・コモ・ショー』を輸入したように、常に視線をアメリカに向けており、テレビという当時の新規メディア通して、アメリカの音楽やそれに準ずるカルチャーを紹介し続けた。またザ・ピーナッツやハナ肇とクレージーキャッツが活躍した『シャボン玉ホリデー』、深夜番組の金字塔である『11PM』、数多くのアイドルを生んだ『スター誕生!』等を企画するなど、細野に「この人が居なかったら今の自分は存在していない」とまで言わせる名プロデューサーだった。表立ってメディアに取り上げられないような裏方の存在ではあったが、けして井原抜きに日本のテレビ史の文脈を語ることはできない。
そのほか、作曲家レモンド・スコットのように、ほとんど前景化してこないが後世のミュージシャンに図らずも多大な影響を与える優れた音楽家も、細野は挙げていた。考古学者のように堆積した歴史の地層をつぶさに観察し、未知なる特異なタレントを発掘しては人々に伝えていくこと、またそこに細野自身の音楽体験を交えて次世代へと有機的に繋げていくこと、それこそが自分の役目であると話していた。